岩手県盛岡市で「森田小児科」を開業しています、院長の森田 順です。
当院は「科学的根拠に基づいた医療(EBM: Evidence Based Medicine)の提供」を治療方針としてかかげ、闇雲に検査をするのではなく、病歴と身体診察を重視した診療を心がけています。
私は医大を卒業後、当時厳しいという評判のあった「沖縄県立中部病院」でスーパーローテート研修(内科・外科・産婦人科・麻酔科・精神科・救急科・小児科・NICU)を行いました。すぐに検査するのではなく、患者さんの病歴と身体診察を重視する病院で、私の医師としての基礎はそこで叩き込まれました。
日本各地を周り、今、自分の育った地域、岩手県で、健康面で皆様のお手伝いができることに、喜びを感じています。社会は絶えず目まぐるしく変化し、ニーズも変わってきましたが、その変化に対応しつつ、皆様のお役に立てるよう今後とも努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
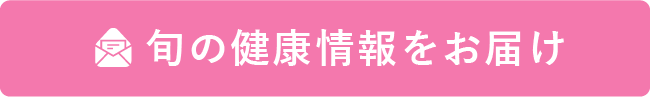

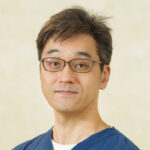
 手足口病とは、ウイルス感染によって発症する病気で、生後6ヶ月くらいから4〜5歳の乳幼児が夏にかかりやすい感染症です。
手足口病とは、ウイルス感染によって発症する病気で、生後6ヶ月くらいから4〜5歳の乳幼児が夏にかかりやすい感染症です。 手のひら、足の裏や甲、口の中などに、米粒大のブツブツとした水疱が出ます。
手のひら、足の裏や甲、口の中などに、米粒大のブツブツとした水疱が出ます。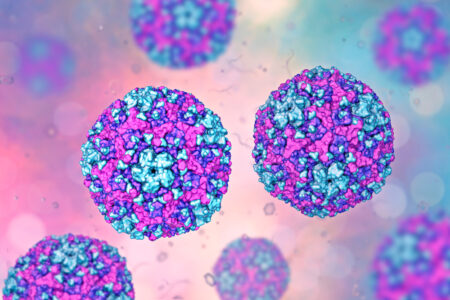 手足口病の主な原因ウイルスは、
手足口病の主な原因ウイルスは、
 基本的には症状の問診と診察だけで診断をします。
基本的には症状の問診と診察だけで診断をします。 手足口病の場合、休むべき日数に明確なルールはありませんが、
手足口病の場合、休むべき日数に明確なルールはありませんが、






