ストレスは自律神経のバランスを崩し、交感神経が過剰に働く状態(緊張・警戒モード)が続くことで、以下のような身体症状を引き起こします
- 頭痛、肩こり、腰痛
- 胃痛、下痢・便秘、食欲不振
- 動悸、息苦しさ、めまい
- 慢性的な疲労感・倦怠感

ストレスは心と体のさまざまな病気・症状に影響を与えます。
ストレスが過剰になってしまうと、自律神経のバランスが崩れて、血流が悪くなり、脳に必要なエネルギーを与えることができなくなります。
脳には心身をコントロールするという重要な役割があるため、脳が疲れたままの状態であれば心や体にさまざまな不調が現れます。
本記事では、心療内科の医師に監修していただき、ストレスがたまると起こる症状とイライラする原因、心が壊れる前兆を解説しています。
目次
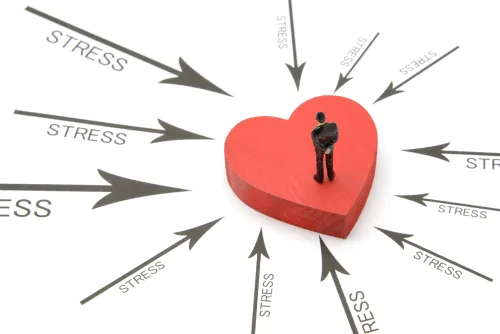 ストレスは本来、物理学の分野で使用されていた用語で「物体からかけられた圧力によって、ゆがみが生じた状態」を意味します。
ストレスは本来、物理学の分野で使用されていた用語で「物体からかけられた圧力によって、ゆがみが生じた状態」を意味します。
医学的には外部からの刺激を受けて生じる体の反応を「ストレス反応」といい、その原因となるものを「ストレッサー」とよびます。わたしたちが普段使用する「ストレス」には、この両方の意味が含まれています。
本来、ストレスを感じると、体内ではそれを解消しようとする防御反応がはたらきます。対処法は人それぞれ異なりますが、ストレスの原因が同じでも、それを受け止める方によってときに「良いストレス」になることもあれば「悪いストレス」になることもあるのです。
「ストレッサー(ストレスの原因)」と「受け止め方」の結果として、ストレス(心身に生じた反応、ゆがみや変調)が生まれます。
ストレスを引き起こす原因は、
など、いくつかの種類があります。
| 心理的・社会的ストレッサー | 緊張、不安、悩み、焦り、寂しさ、怒り、惜しみなど 仕事や家庭などで起こる人間関係や社会的立場など、日常の社会生活をおくる上で起こるストレス要因 |
|---|---|
| 物理的ストレッサー | 温度(暑い・寒い)、騒音、明るい光など 物理的な環境刺激によって起こるストレス要因 |
| 化学的ストレッサー | 公害物質、金属、アルコール・タバコ、食品添加物など 主に体へ害のある化学物質によって起こるストレス要因 |
| 生物的ストレッサー | アレルギー物質による炎症、ウイルス・細菌への感染など 生物が関連して起こるストレス要因 |
 過剰なストレスを抱えると、
過剰なストレスを抱えると、
上記のような症状が現れます。
さらに、これらの状態が続くと、
など、普段の生活に支障をきたしてしまうことも少なくありません。
また、
このような感情が出てきたときには、なんらかの精神疾患を発症している可能性も否定できません。
なるべく早めに医療機関を受診してください。
 ストレスが身体の症状として現れる場合もあります。
ストレスが身体の症状として現れる場合もあります。
など、睡眠障害と言える症状がみられることが多いです。
また、
などのがみられる場合があります。
など、ストレスはさまざまな症状を誘発させる引き金となります。
 ストレスは心と体のさまざまな病気・症状に影響を与えます。ストレスが過剰になってしまうと、自律神経のバランスが崩れて、血流が悪くなり、脳に必要なエネルギーを与えることができなくなります。
ストレスは心と体のさまざまな病気・症状に影響を与えます。ストレスが過剰になってしまうと、自律神経のバランスが崩れて、血流が悪くなり、脳に必要なエネルギーを与えることができなくなります。
脳には心身をコントロールするという重要な役割があるため、脳が疲れたままの状態であれば心や体にさまざまな不調が現れます。
うつ病は落ち込みや心配を感じ、日常の活動に意欲や関心、喜びなどの感情を見出せなくなる病態です。うつ病の症状としては、落ち込んだ気分や悲しみが続き、自尊心の低さ、絶望感や無力感、涙もろくなること、強い罪悪感、いらだちやすく他者に不寛容になることなどがあげられます。
診察のポイントは、症状がどの程度長く続いているのかという点です。目安として、うつ病を疑う症状が2週間以上続く場合、うつ病と診断される可能性があります。その際は、別の疾患が抑うつ(気分が落ち込こむ、何にもする気になれない等)の症状を引き起こしている可能性を除外するために、血液検査を勧めることもあります。
適応障害はストレスに関連する短期的な精神疾患で、主に重大なライフイベント(人生における出来事)を経験しているときに起こることがあります。大人であれば職場で重要な仕事を任されたり、転勤などの新しい環境に馴染めなかったり、強いストレスのかかる出来事は人それぞれです。子どもの場合は、家族の不和、学校での問題、病気やケガによる入院などがきっかけとなることもあります。
いずれもきっかけとなるストレスがそこまで深刻ではない場合をさし、患者さんの反応はその出来事の内容とは不釣り合いにストレスが強かったり、期間が長すぎたりするのが特徴です。通常は、状況に適応する方法を自然と身につけたり、ストレス要因がなくなったりすることで、数ヶ月以内には治ります。
心配事やストレスなどがきっかけとなり、眠りにつくことや翌日すっきりと回復感を得られるくらい長く眠り続けることが困難になる病気です。なかなか寝付けない、夜間に繰り返し眼が覚める、などの症状が続き、疲労が溜まってしまうことでさらにイライラや不安が起こり、物事への集中ができなくなります。
心配事やストレスの原因は人それぞれで、仕事や家庭でのトラブル、金銭的な問題、親しい相手との死別など、日々の生活の中で起こる重大な出来事をはじめ、自身の健康上の影響(病気になった、など)、アルコールや薬物の使用も引き金となる場合があります。 短期で治ることもあれば、数ヶ月・数年と長期化してしまうこともあります。高齢者に比較的多く見られる病気です。
突発性とは「突然・急に」という意味で、これまで問題なく機能していた聴力に突然何の前触れもなくトラブルが生じ、耳が聞こえなくなる病気です。 音がこもる、耳が詰まった感じがするという症状があげられます。
突発性難聴は、耳の奥深くのウィルス感染や血流障害が主な原因となっていると考えられていますが、明確な原因は未だわかっていません。 また、健康な方が突然発症することも少なくないため、近年は疲労やストレス過多なども原因のひとつとして考えられています。
睡眠不足や肉体的な疲労によって身体的なストレスが過剰になったり、不安やいらだちなど精神的なストレスが続くと、やがて自律神経が乱れていきます。それによって内耳の血流トラブルを招くのではないかと推測されています。
過敏性腸症候群(IBS)は、腸が過剰に敏感になっている症状がみられる病態です。大腸に腫瘍や炎症などの病態がないにもかかわらず、お腹の不快感や便通の異常が数ヶ月以上続く場合、過敏性腸症候群と診断されます。その原因のひとつが「ストレス」です。
ストレスが自律神経のバランスを崩すことによって、消化や吸収、排泄などが正常に機能しなくなることで起こります。日常生活の中で、ちょっとしたストレスを感じるとお腹が痛くなり、慢性的にお腹周りが重苦しく、いつ腹痛を発症するのかという不安がさらにストレスを招区という悪循環に陥ります。まずはどんなんときにどのような症状で困っているのかを自分自身が理解しておくことが大切です。
アルコール依存症は、お酒の飲み過ぎによって何らかの問題が起こっているのにも関わらず、自分ではその飲み方をコントロールできなくなっている状態のことをいいます。健康な方は、お酒の飲み方を自分で調整できますが、依存症の方は「量・時間・状況」という3点で、コントロールできないのが特徴です。
アルコールの適度な摂取には、気持ちをリラックスさせたり、血流のながれを良好にしたりする効果があります。人によってはストレス解消をもたらす効果がある一方で、アルコールへの依存が強くなると、お酒を飲めないことがストレスとなり、酒量が増えるというパターンを繰り返すことになります。
心身に不調が生じるばかりではなく、周囲の人に多大な迷惑をかけたり、それによって社会的な信用を失うなどのさまざまな悪影響を及ぼしてしまうため、早めに適切な治療を受けることが大切です。
拒食症と過食症という病気を合わせて、摂食障害といいます。
過食症とは、食欲を抑えることができず短時間で大量に食べたり、ダラダラと食べ続けたりする病態です。結果的に体重増加を避けるために吐くか下剤を使って防ぐなど、体に負担のかかる行為を繰り返し、そのような自分に嫌悪感や罪悪感を抱くようになります。
拒食症は食べること極端に拒否してしまう病気で、極端に痩せてしまいます。自分では痩せている意識がなく、体重が増えてしまうことや食事量を増やすことに対して強い不安や恐怖を感じます。
摂食障害は診断がつきやすい一方で特効薬はなく、病気を認めない方も少なくないため、治療が難しい病気です。病気の治療には、患者さん自身の意思がとても大切となるため、まずは正しい知識を得ることが重要です。
胃腸に炎症が起こる原因はさまざまですが、中でもストレスや不安が原因で起こる病気をストレス性胃腸炎といいます。そもそも胃腸は、ストレスに非常に敏感な臓器です。ストレス過多にあると、自律神経のバランスが乱れて、胃腸のはたらきに影響を及ぼします。
自律神経の交感神経が優位になると胃酸の分泌や胃の運動が減りすぎてしまい、その状態を回避するために副交感神経が活発になると、今度は胃酸の分泌や胃の運動が増えすぎてしまいます。ストレス性胃腸炎は、この状態がくり返されることによって胃酸が胃粘膜を傷つけ、炎症を起こす病気です。
ストレスは自律神経のバランスを崩し、交感神経が過剰に働く状態(緊張・警戒モード)が続くことで、以下のような身体症状を引き起こします
脳は心と体の状態を統合的にコントロールしています。脳が疲弊すると、身体の調整機能も乱れ、以下のような不調が現れます
はい。ストレスは脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリン)の分泌を低下させ、情緒が不安定になりやすくなります。 その結果、以下のような状態に陥ることがあります
強いストレスが長期間続くと、脳の神経ネットワークの働きが低下し、以下の精神疾患を発症することがあります
以下のような変化が2週間以上続いている場合、限界が近づいているサインかもしれません
あります。慢性的なストレスは、脳の「前頭前野」や「海馬」の機能低下を引き起こすことが分かっています。
これにより、
ストレスにより交感神経が優位なままになると、脳が“興奮状態”になり、入眠しづらくなります。
また、寝ても中途覚醒が多く、朝まで熟睡できないこともあります。睡眠不足が続くと、
以下のような状態が続く場合、医療機関での相談をおすすめします。
ストレスをゼロにすることは難しいですが、「ため込まずに、発散できる仕組みを作る」ことが大切です。
具体的には
基本的には心療内科または精神科が専門領域です。
ただし、「体の不調が中心だけどストレスが関係していそう」という場合は、

からだとこころのクリニックラポール佐竹 学 先生
宮城県仙台市の心療内科、からだとこころのクリニックラポールでは、身体疾患にも精神疾患にも対応しています。そのため、症状や原因別にそれぞれ違う病院に通って頂く必要はありません。
場合によっては、專門治療を行っている大学病院などにご紹介させて頂くこともございますが、まずは当クリニックにお越し頂ければ、適切な検査と診断を行い、患者さまにとって最も良いと思われる治療方針をご提案させて頂きます。
身体の症状にせよ、心の問題にせよ、患者さまがお持ちのお悩みは全て真正面から受け止めるようにしています。
職場や家庭についての不満、転職や転勤など環境変化による不安など、何でもお気軽にお話しください。
© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.