熱がなくても、痛みが続く・繰り返す・生活に支障をきたす場合は、安易な判断は避けましょう。
特に、朝方に起きる強い頭痛や、活動中に急に泣き出す・黙り込むような様子がある場合は早期の受診が望まれます。重大な疾患を見逃さないためにも、迷ったら小児科に相談してください。

子どもの頭痛は、ご家族の方々にとっても何か病気が隠れていないか心配になる症状です。頭痛は、原因となる病気がない頭痛と、原因となる病気がある頭痛の2つのパターンに分類できます。
大人は「頭が痛い」という自覚症状はありますが、子どもに頭痛の症状がでた場合、必ずしも「頭が痛い」と表現するとは限りません。黙ってしまって様子が変だったり、だるさを訴える場合もあります。年代によってもその訴え方は変わってきますので、お子さんのサインを見逃さないことが重要です。
本記事では小児科医に監修していただき、子どもの頭痛の対処法、「頭が痛いけれど、熱はない」という場合に懸念される原因を解説しています。
目次
 子どもが「頭が痛い」と訴えたとき、どのような原因が考えられるのかを知っておくと落ち着いて対処できます。
子どもが「頭が痛い」と訴えたとき、どのような原因が考えられるのかを知っておくと落ち着いて対処できます。
頭痛にはさまざまなタイプがありますので、まずは様子を見ても大丈夫な頭痛と、危険を伴い早期の受診が必要な頭痛を、大まかに把握しておきましょう。
頭痛は大きく分けて、
この2つのタイプに大別されます。
一般外来でとくに多い頭痛は、風邪などの感染症によって起こる頭痛です。とくに小学校低学年以下では、この感染症が原因によって頭が痛いと訴える方が多数みられます。
同時に発熱などの風邪症状がみられ、風邪が治ると頭痛の症状も治ります。そのため、とくに心配はいらない頭痛といえます。
発熱がない場合、またはすでに熱が下がっているにもかかわらず強い頭痛がある場合は、保護者の方も「どうして?」と不安になることでしょう。
発熱のない頭痛で受診する場合、
以上が原因となって起こる頭痛が比較的多いです。
もっとも多い頭痛の発症原因は「片頭痛」です。片頭痛は一次性頭痛に分類されます。
次に多いのは、緊張型頭痛とよばれるタイプの頭痛です。こちらも一次性頭痛に分類されます。なかでも時々、頭痛が繰り返し起こる「反復性緊張型頭痛」は、軽度から中等度の頭痛で、念のため一度受診しておくと安心です。
救急外来でも感染症による頭痛患者さんは多いですが、次によく見られるのは、ケガによって起こる頭痛です。頭部外傷によって起こる頭痛は、夜間に強い頭痛で嘔吐してしまい、救急外来を受診するというケースがあります。
 頭痛だからといって、子どもが「頭が痛い」と表現するとは限りません。いつも元気なお子さんが「黙ってしまって様子が変」と感じたり、「食事のときに普段と比べても食べないので、不思議に思った」ということもあります。
頭痛だからといって、子どもが「頭が痛い」と表現するとは限りません。いつも元気なお子さんが「黙ってしまって様子が変」と感じたり、「食事のときに普段と比べても食べないので、不思議に思った」ということもあります。
とくに、だるさ・疲労感を訴える場合は、背景に片頭痛の症状が起こっていることも少なくありません。
普段からよくお子さんの様子を観察することが大切です。
子どもの片頭痛には、予兆・前兆となる特徴があります。
などがあげられます。
これらの症状が、片頭痛発症前、数時間〜2日程度を目安に起こる傾向があります。
また、
など、視覚前兆がみられる場合があります。これを閃輝暗点(せんきあんてん)といいます。
この視覚前兆は、片頭痛発症前、5〜60分程度の間にみられる症状です。
子どもの片頭痛は、前述した予兆・前兆がある他
これらの特徴があります。
片頭痛がはじまると、光や音を避けたい(光過敏、音過敏)状態になり、暗く静かな部屋に行って寝てしまうケースも多いです。
強い頭痛によって日常的な行動ができなくなる場合もあります。悪心(吐き気、気持ち悪い)や嘔吐の症状がみられることもありますので、注意しましょう。
痛みが治まってからしばらくは、疲労感や集中困難、肩こりなどの後発症状があらわれることがあります。ただし、片頭痛の症状が始まる頃には子どもは眠ってしまうことも多いため、起きたあとは症状が消えて後発症状はあまりはっきりしないこともあります。
片頭痛の持続時間は、寝てしまった場合は起きるまでの時間として、18歳未満では2時間以上とされています。
予兆・前兆から片頭痛がはじまり、やがて頭痛の症状が落ち着くまで、だるさが続き食欲もなくなることも少なくありません。その耐め、片頭痛発作が多いお子さんは体重減少が心配される場合もあります。注意深く、日々の生活を送るよう心がけましょう。
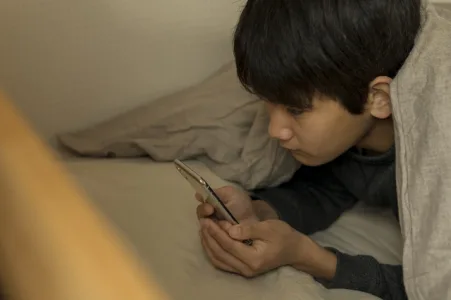 頭痛にはさまざまなタイプがあり、片頭痛は「原因となる病気のない一時性頭痛」に分類されます。そのため、片頭痛発生の原因、そのメカニズムはまだ明らかになっていません。
頭痛にはさまざまなタイプがあり、片頭痛は「原因となる病気のない一時性頭痛」に分類されます。そのため、片頭痛発生の原因、そのメカニズムはまだ明らかになっていません。
一方で、いくつか片頭痛を誘因するもの(引き金)が考えられます。
など、寝不足によって片頭痛発作が増えたというケースがあります。
部活中にバレー部に所属して、体育館の天井のライトを見ると頭が痛くなるという事例がありました。
また、雨が降る前や台風が発生したときなど、気圧の変化が影響して起こる場合も考えられます。これは、大人も同様に誘発要因として考えられています。
など、食べ物が誘因と考えられるケースもあります。
お子さんと同じく、お母さんも同様の食品を口にした際に片頭痛を発症するなど、親子で共有の食べ物が原因となっている場合もみられます。
食品のほかにも、なんらかの匂いに反応して片頭痛を発症するケースもあります。
初経以降の女児は、月経時期や排卵日に片頭痛発作が起きることがあります。
とくに月経関連で起こる片頭痛は、成人女性と同様に、頭痛が長引く傾向があり、薬も効きにくくなる特徴があります。
現在、発症要因として有力とされているのは、性別と年齢に応じて有病率が変動しますが、特に3〜7歳の男の子に多く、15歳以降では女の子に多くみられます。7〜11歳は男女平等でみられます。
子どもの片頭痛は大半が軽度ですが、稀に、頭痛発作が繰り返され吐き気が伴うケースも存在します。
片頭痛の次に多く見られるのは、緊張型頭痛です。この緊張型頭痛も一次性頭痛で、とくに小学校の高学年から高校生にかけて、1カ月に15回以上、3カ月以上も続く緊張型の慢性頭痛が発生します。
子どもの緊張型頭痛は、スマホや電子デバイスの過度な使用による姿勢の悪化や、趣味や学校のストレスからも引き起こされることが多いです。
緊張型頭痛は長引く傾向がありますが、片頭痛ほど日常生活に支障をきたす強い症状はありません。一方で、悪心や嘔吐も起こらず、頻度は1カ月に1日以下から半月以上に及ぶものまであります。
子どもの片頭痛には薬物治療もありますが、最初は「非薬物療法」から始めることが推奨されています。基本的な対策は、早寝早起きと朝食、適度な運動、そして正しい姿勢を保つことです。
ただし、子供が頭痛の症状で度々学校を休んだり、他の活動に参加できないような場合には、専門の医師に相談することが必要です。特に、頭痛の発症が急で症状が重篤な場合や、他の体調不良が同時に出た場合は、即座に医療機関にかかることが求められます。
脳に異常がある場合など、なんらかの病気が原因が原因で起きる頭痛を二次性頭痛といいます。
原因が治れば頭痛は大幅に軽減または消失する可能性が高い一方で、ときに重篤な病気であることが多いため注意が必要です。
頭痛が発熱と一緒に出る場合は二次性頭痛と診断されます。
吐き気の症状がみられれば「髄膜炎」、意識障害やけいれんがあれば「脳炎」の疑いがあります。
発熱が伴わない場合には、もやもや病や脳腫瘍、稀にくも膜下出血などの重篤な病気も懸念されます。
以上のように、二次性頭痛は時折、重篤な疾患が背景にあるため、症状の程度や急性度、他の症状をよく観察して、異変があればすぐに医療機関にかかるようにして下さい。
熱がなくても、痛みが続く・繰り返す・生活に支障をきたす場合は、安易な判断は避けましょう。
特に、朝方に起きる強い頭痛や、活動中に急に泣き出す・黙り込むような様子がある場合は早期の受診が望まれます。重大な疾患を見逃さないためにも、迷ったら小児科に相談してください。
以下のような症状は、脳の異常や神経の病気を示唆する可能性があるため、至急受診が必要です。
はい。
小さなお子さんや言葉でうまく表現できない子どもは、不機嫌になる、遊ばなくなる、頭を押さえる、黙り込む、泣き出すなど、行動で異変を示すことがあります。こうした変化は、頭痛のサインとして慎重に観察する必要があります。
子どもの頭痛は、多くが緊張型頭痛(肩や首のこりなど)や片頭痛に分類されます。
2025年の頭痛診療ガイドラインでは、これらの原因に加えて、生活習慣の乱れやデジタル機器の長時間使用、心理的ストレスなども明確に関連因子として示されています。
はい。
近年の調査では、1日3時間以上のスマートフォン・タブレット使用で頭痛リスクが明らかに上昇することが報告されています。姿勢不良やブルーライトによる睡眠障害・生活リズムの乱れも頭痛の誘因になります。家庭では使用時間・姿勢・就寝時間に関するルールづくりが強く推奨されています。
子どもの片頭痛は、痛みの持続時間が短い一方で、腹痛や嘔吐、光や音に対する過敏さを伴いやすい傾向があります。
また、前兆(チカチカする光など)を伴う片頭痛も少なくありません。大人よりも見逃されやすいので、保護者の気づきが大切です。
不登校や登校しぶりと頭痛は、心理的ストレスや自律神経の乱れと関連している場合があります。
2025年のガイドラインでは、子どものメンタルヘルスと頭痛の関連性に注目した非薬物的アプローチ(カウンセリングやストレスマネジメント)の活用が推奨されています。
静かな部屋で休ませたり、部屋を暗くして落ち着ける環境を整えることが大切です。
水分補給や十分な睡眠、画面からの休憩なども効果的です。強い痛みがなければ、軽い運動やストレッチも改善につながることがあります。ただし、市販薬の使用は自己判断せず、小児科医の指示を仰ぎましょう。
まずは小児科の受診が基本です。
必要に応じて、小児神経科や脳神経外科、専門の頭痛外来に紹介されることもあります。最近では、症状が比較的軽度な場合や、経過観察をしながら相談したいときに、オンライン診療を活用する例も増えています。
頭痛予防には、規則正しい生活リズム、十分な睡眠、栄養バランス、適度な運動、スクリーンタイムの管理が効果的です。
また、家庭での会話やストレスケアの時間を設けることも、心因性の頭痛の予防につながります。日記やカレンダーに頭痛の頻度や時間帯を記録しておくと、医師との相談にも役立ちます。

西島こどもクリニック西島 浅香 先生
当院では、お子様の病気や健康についての相談、健康診断や予防接種についての相談をはじめ、併設の「西島産婦人科医院」と協力・連携しながら、子育て中のご両親の支援も積極的に行っております。
お子さん、ご両親との係わりの中から健康な家庭が築けますよう願いつつ診療しております。
生活環境や食物等の変化に伴い増加してきた、お子様のアレルギー疾患(気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など)にも対応しております。
また、子育て一般についても気軽にご相談下さい。
地域における”こどもの心相談医”として、ぜひお気軽にご相談ください。
© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.