はじめまして「大通公園メンズクリニック」の院長、西澤康平です。
全国のメンズクリニック院長として長年培った経験とノウハウを元とし、これまでにないメンズクリニックを作りたいという思いから、この度当院を開院することとなりました。
当院は、薬剤の効果や服用上の注意点については勿論のこと、費用面についてもしっかりとご説明をして、全ての患者様に対して不安なく受診していただける「わかりやすさ」をモットーとしたクリニックです。
また、プライバシー保護や、土日、祝日、平日夜間も診察を受付けることで、いつでも立ち寄っていただける、患者様の立場に立った「利用しやすさ」にも力を入れています。
アクセスは地下鉄大通駅徒歩1分、地下歩行空間直結(26番出口直結)となっておりますので雨や雪の日も安心して通って頂けます。
みなさまのご来院を心よりお待ち申し上げております。
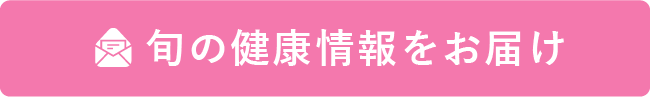

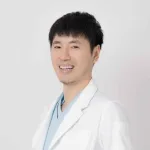
 わたしたちはほとんど毎日、寝ては起きるを繰り返す生活を送ります。人生のおおよそ3分の1は寝て過ごしていることになります。
わたしたちはほとんど毎日、寝ては起きるを繰り返す生活を送ります。人生のおおよそ3分の1は寝て過ごしていることになります。