消化器内科は、食道・胃・小腸・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓などの「消化器官」を専門に診る内科の一分野です。
私たちが食べたものを体が正常に消化・吸収・排泄するために欠かせない臓器の機能を支える役割を担っており、食欲不振や腹痛、便通異常、黄疸など、さまざまな症状の原因を突き止めて治療を行います。かつては「胃腸科」と呼ばれていたこともありますが、現代ではより広範囲の病気に対応する総合的な診療科として確立されています。

この記事でわかること
札幌市には消化器内科の専門医が多数在籍しており、胃や腸の病気はもちろん、肝臓・胆嚢・膵臓の疾患にも対応可能です。特に、札幌医科大学附属病院やJR札幌病院などでは、難病や希少疾患の治療にも力を入れています。かかりつけ医(クリニック)で診察・検査を受け、より専門的な治療が必要な場合は総合病院へスムーズに紹介されるため、必要な医療を無駄なく受けられます。また、総合病院で高度な治療を受けた後、リハビリや継続治療は地域のクリニックでサポートされるため、長期的なフォローも安心です。
本記事では消化器内科専門医監修のもと、消化器内科とはどのような診療科か、相談すべき症状や病気を解説しています。また「どのクリニックを受診すればいいかわからない」という方に、おすすめの消化器内科クリニック10選をご紹介します。ぜひ、ご参考にしてください。
目次
私たちが毎日口にする食べ物は、体内でどのように消化・吸収されるのかをご存じですか?そのプロセスを支えるのが「消化器」と呼ばれる器官です。
消化器は「食べる」「消化する」「栄養を吸収する」という生命活動の根幹を支える大切な役割を担います。そして、その消化器に関わるさまざまな病気を診断し、治療する専門分野が「消化器内科」です。
かつては「胃腸科」と呼ばれることもありましたが、現在は食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓など 広範囲の消化器系疾患を対象とする「消化器内科」として確立されています。
消化器内科を選ぶ際は、「どのクリニックでも同じ」と思わず、慎重に選ぶことが大切です。内視鏡検査の精度や医師の経験、検査時の快適さは医療機関によって異なります。適切な診療を受けるために、以下のポイントをしっかり押さえましょう。
消化器内科を選ぶ際には、以下のポイントを意識しましょう。
自分に合った病院を選ぶことで、安心して検査や治療を受けることができます。気になる症状がある場合は、早めに消化器内科を受診し、適切な診断を受けましょう。
消化器内科は専門性の高い分野であり、経験や資格によって診療の質が大きく変わります。
消化器内科の専門医資格を持っているかを確認しましょう。特に、日本消化器内視鏡学会の専門医資格がある医師は、内視鏡検査に精通しています。医師の経歴やこれまでの症例を調べ、経験豊富な医師を選ぶことで、より正確な診断と適切な治療を受けることができます。
クリニックの公式ホームページで医師のプロフィールを確認し、実績をチェックすることが大切です。
内視鏡検査は、消化器内科において欠かせない検査の一つです。実績や設備の違いが検査の精度に直結するため、事前に確認しましょう。
年間の内視鏡検査数が多い病院ほど、技術力が高く、スムーズな検査が期待できます。また、最新の内視鏡システムを導入しているかも重要です。高精度な機器を使用することで、小さな異変も見逃しにくくなります。
医療設備の情報も、クリニックの公式ホームページでチェックし、不安があれば事前に問い合わせてみるのも良いでしょう。
忙しい人にとって、検査にかかる時間は重要な要素です。予約が取りやすく、スムーズに検査が受けられるかを確認しましょう。検査の流れや所要時間を事前に確認し、負担の少ないスケジュールを立てることが大切です。
近年ではネット予約も主流になっています。ネット予約を利用すれば、忙しい中でも簡単に予約ができ、待ち時間を短縮し、スムーズに診察を受けられます。特に評判が良く流行っているクリニックに通院したい方や、仕事・育児で時間が限られている方にとって、大きなメリットがあります。
実際に受診した患者さんの声は、医療機関選びの貴重な参考になります。
Googleマップや病院検索サイトの口コミをチェックし、医師の対応や施設の清潔さについて確認しましょう。「説明が丁寧」「スタッフの対応が良い」などのポジティブな口コミが多い病院は、安心して通院できる可能性が高いです。
ただし、個人の感じ方には差があるため、あくまでも参考程度にすることをおすすめします。

| クリニック名 |
さっぽろ白石内科消化器クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南8-10 白石ガーデンプレイス3F |
| 電話番号 | 011-862-8878 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 13:30-18:00 | ● | ● | − | ● | ● | − | − |
休診日/水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
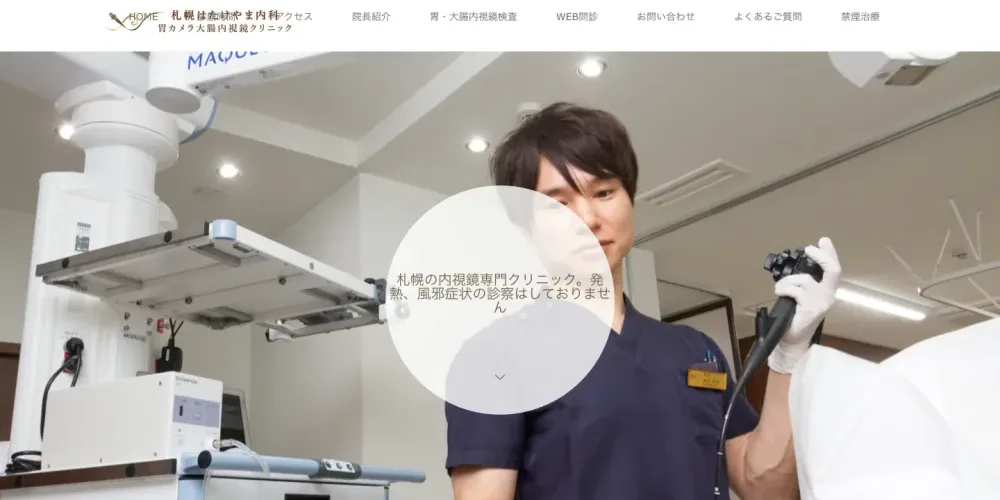
| クリニック名 |
札幌はたけやま内科・胃カメラ大腸内視鏡クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北1条西23丁目2番14号 |
| 電話番号 | 011-688-7950 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-13:00 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 14:30-18:00 | − | ● | ● | ● | ● | ※ | − |
休診日/月曜午後・日曜・祝日
▲月曜は12時までの診療
※土曜13時以降は予約検査のみ

| クリニック名 |
さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西5丁目7-6 第27ビッグ札幌北スカイビル 4階 |
| 電話番号 | 011-700-1110 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:10 | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |
| 15:10-19:10 | ● | ● | ● | ● | − | − | − |
休診日/金曜午後・土曜午後・日曜(第1,3日曜のみ診療)・祝日
▲火・金は午前は12時までの診療
※土・日は8:30~12:00までの診療
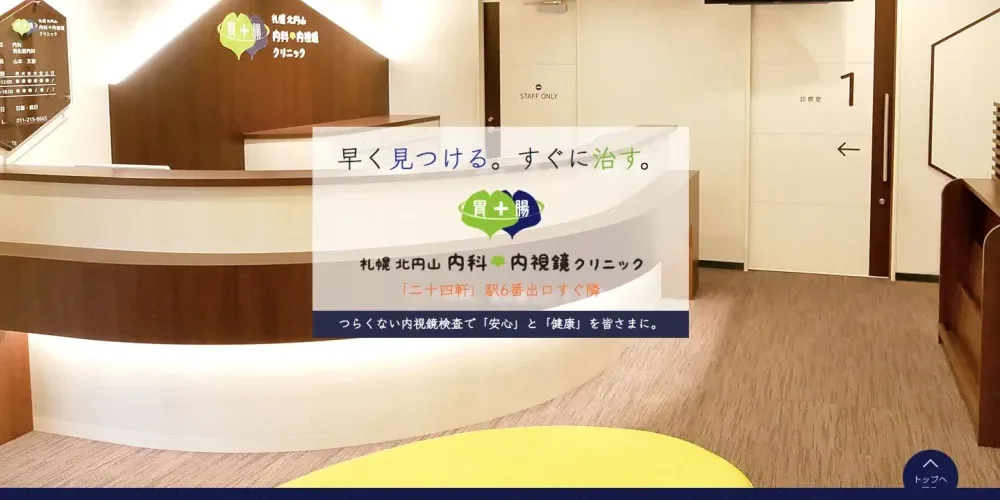
| クリニック名 |
札幌北円山内科・内視鏡クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒1条5丁目1−34 メディカルスクエア北円山 2F |
| 電話番号 | 011-215-6665 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 14:00-18:00 | ● | ● | ● | − | ● | − | − |
休診日/木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

| クリニック名 |
ほんじょう内科 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸1条12丁目1番30号 メディカルスクエア南平岸 2F |
| 電話番号 | 011-595-8261 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − |
| 14:30-18:00 | ● | ● | ● | − | ● | ● | − |
休診日/水曜・日曜・祝日
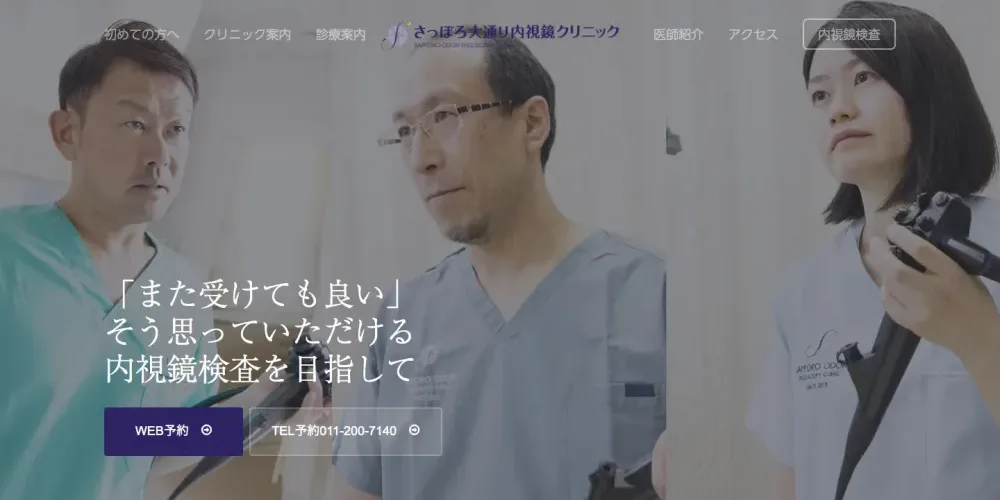
| クリニック名 |
さっぽろ大通り内視鏡クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西4丁目6番地1 札幌大通西4ビル5階 |
| 電話番号 | 011-200-7140 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | − |
| 14:00-17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | − | − |
休診日/土曜午後・日曜・祝日
▲土曜は13時までの診療

| クリニック名 | ひらた内科・内視鏡クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区北4条東7丁目375 イニシアグラン札幌イースト1階 |
| 電話番号 | 011-522-8344 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:15 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | − |
| 14:00-17:00 | ● | ● | − | ※ | ● | − | − |
休診日/水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
▲水・土は13時までの診療
※木午後は18時までの診療
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
| クリニック名 |
こんの内科・消化器内科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似2条1丁目1-52 |
| 電話番号 | 011-299-4107 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 14:00-18:00 | ● | ※ | ● | − | ● | − | − |
休診日/木曜午後・土曜午後・日曜・祝日
※火午後は予約検査のみ
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
| クリニック名 |
|
|---|---|
| 住所 | |
| 電話番号 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 14:00-18:00 | ● | ● | − | ● | ● | − | − |
休診日/水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
| クリニック名 |
|
|---|---|
| 住所 | |
| 電話番号 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − |
| 14:00-18:00 | ● | ● | − | ● | ● | − | − |
休診日/水曜午後・土曜午後・日曜・祝日
消化器内科は食道・胃・腸・肝臓・胆嚢・膵臓など、消化器系のトラブルを専門的に診る診療科です。 「ちょっとした不調だから…」と放置してしまうと、重大な病気のサインを見逃す可能性もあります。
では、どのような症状があると消化器内科に相談すべきなのでしょうか?
これらの症状がある場合、消化器系のがんや炎症性疾患の可能性も考えられるため、早めに受診しましょう。
消化器系の病気は、早期発見・早期治療が重要です。放置すると症状が悪化し、治療が難しくなることもあります。 「大したことないかも…」と思っても、一度専門医に相談して 安心を得ることが健康への第一歩 です。気になる症状があれば、早めに消化器内科を受診しましょう!
消化器内科では、以下のような幅広い疾患を専門的に診療します。
など
これらような早期発見と治療が重要な疾患も、消化器内科の重要な診療領域です。
消化器内科では、胃や腸、肝臓、胆嚢、膵臓などの病気を早期に発見し、適切な治療を行うことを目的に、さまざまな検査や治療法が用いられます。ここでは、具体的な検査方法と治療法について詳しく解説します。
内視鏡を用いて、食道、胃、十二指腸、大腸の内部を直接観察する検査です。炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの異常を発見でき、必要に応じて組織の一部を採取(生検)して詳しく調べます。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)では、口または鼻からスコープを挿入し、食道や胃の粘膜の状態を確認します。胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎、胃がんの早期発見に有効で、ピロリ菌感染の有無も確認できます。
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)では、肛門からスコープを挿入し、大腸の内部を観察します。大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の診断が可能です。ポリープが見つかった場合、その場で切除することもあります。
検査前には胃や大腸の内容物を除去するため、食事制限や下剤の服用が必要です。鎮静剤を使用することで、痛みや不快感を軽減できます。
皮膚の上から超音波を当てて、肝臓、胆嚢、膵臓などの臓器の状態をリアルタイムで観察する検査です。
肝臓の脂肪変性(脂肪肝)、肝硬変、肝がんの診断に有効で、胆石や胆嚢炎の有無、膵臓の腫瘍や炎症の有無も調べることができます。
X線やCTと違い、被ばくの心配がなく安全で、痛みもなく短時間で終わるのが特徴です。
体の内部を詳しく調べるための画像診断です。
CT検査(コンピューター断層撮影)は、X線を使用して消化器の断面画像を撮影します。がんや炎症、腸閉塞、腹部の出血などを詳しく調べるのに適しています。
MRI検査(磁気共鳴画像診断)は、磁場と電波を利用してより精密な画像を取得できます。肝臓、胆嚢、膵臓の腫瘍や、胆管・血管の異常を詳しく調べるのに適しています。
CTは短時間(5〜10分)で撮影できますが、X線被ばくがあります。一方、MRIは被ばくなしで詳細な画像が得られますが、撮影時間が長く、閉所恐怖症の方には不向きな場合もあります。
血液を採取し、肝機能、膵臓の状態、炎症の有無、腫瘍マーカーなどを調べます。
AST・ALT(肝機能)では肝炎や肝障害の有無を確認し、ALP・γ-GTP(胆道系)では胆石症や胆管炎の可能性を調べます。CEA・CA19-9(腫瘍マーカー)は、消化器系のがんのスクリーニングに用いられます。
血液検査だけで病気を確定することはできないため、他の画像検査と組み合わせて診断を行います。
症状や病気に応じて、適切な薬を使用します。
胃酸を抑える薬(PPI・H2ブロッカー)は胃潰瘍や逆流性食道炎の治療に用いられ、抗ウイルス薬はB型・C型肝炎の治療に使用されます。潰瘍性大腸炎やクローン病には免疫抑制剤や抗炎症薬が処方されることがあります。
内視鏡を使って、ポリープや早期がんを切除する治療法です。
大腸ポリープは、内視鏡的ポリープ切除術(EMR)によって取り除くことで、将来のがん化を防ぐことができます。また、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を用いれば、早期の胃がんや大腸がんを切除することが可能です。
開腹手術を行わずに治療ができるため、体への負担が少ないのが特徴です。ただし、がんの進行度によっては、追加治療が必要になる場合もあります。
食生活や生活習慣の見直しを指導し、病気の予防や症状の改善を目指します。
脂肪肝の改善にはバランスの取れた食事と適度な運動が推奨され、胃腸の不調を防ぐためには食物繊維の摂取やストレス管理が重要です。逆流性食道炎の対策として、食後すぐに横にならない、寝る姿勢を工夫するなどのアドバイスが行われます。
進行がんや再発防止のために、抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤などを使用します。最近では個別化医療が進み、患者ごとに最適な治療法が選択されるようになっています。
消化器内科では、早期発見と早期治療が重要です。
定期的な検査を受けることで、病気の予防や早期治療が可能になります。特に内視鏡検査では、がんの早期発見ができるため、健康診断の一環として積極的に受診することが推奨されます。
気になる症状がある場合は、できるだけ早めに専門医に相談しましょう。
消化器内科は、食道・胃・小腸・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓などの「消化器官」を専門に診る内科の一分野です。
私たちが食べたものを体が正常に消化・吸収・排泄するために欠かせない臓器の機能を支える役割を担っており、食欲不振や腹痛、便通異常、黄疸など、さまざまな症状の原因を突き止めて治療を行います。かつては「胃腸科」と呼ばれていたこともありますが、現代ではより広範囲の病気に対応する総合的な診療科として確立されています。
消化器内科では、以下のような症状を相談することができます。
症状や疑われる疾患に応じて、以下のような検査が行われます。
内視鏡検査に不安を感じる方は多いですが、最近では医療技術の進歩により、負担の少ない検査が可能になっています。
たとえば、経鼻内視鏡を用いた胃カメラは、口からよりも嘔吐反射が起きにくく、会話も可能なまま検査できます。また、多くの施設では鎮静剤(静脈麻酔)を使用し、眠ったような状態で検査が受けられます。大腸カメラについても、空気の代わりに炭酸ガスを使用することで、検査後の張り感を軽減する工夫がされています。 検査が不安な方は、事前に「苦痛を軽減する方法があるかどうか」を確認しましょう。
消化器内科は、主に内視鏡や薬物療法によって治療を行う診療科です。
たとえば、胃潰瘍や肝炎、過敏性腸症候群などの慢性疾患に対して、内科的なアプローチで症状を改善していきます。
一方、消化器外科は、手術を中心とした治療を行う診療科で、がんや胆石症、腸閉塞など、外科的介入が必要なケースに対応します。まずは内科を受診し、必要に応じて外科に紹介されるのが一般的な流れです。
以下のような場合には、かかりつけ医(クリニック)から総合病院へ紹介されることがあります。
症状が軽い・初期の段階であれば、まずは消化器内科のあるクリニックの受診がおすすめです。
丁寧な問診と初期検査により、必要があれば病院へ紹介されます。 逆に、以下のようなケースでは、初めから病院を受診した方がよい場合もあります
多くの消化器内科クリニックでは、予約優先制、または完全予約制を採用しています。
特に胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査は、前日の食事制限や下剤の服用が必要なため、事前予約が必須となります。
一部の施設では当日診療も可能ですが、待ち時間が長くなることがあるため、なるべく早めに予約を取りましょう。Web予約や電話受付に対応している医療機関も増えています。
「どの科を受診すればいいかわからない」という方こそ、消化器内科の受診をおすすめします。
腹痛や下痢といった典型的な症状だけでなく、食欲不振・疲労感・体重減少・微熱などの全身的な症状の背景に、消化器疾患が潜んでいるケースも少なくありません。 消化器内科では、問診・視診・触診・検査を通じて的確に病気を見つけ、必要に応じて他科への紹介も行います。
消化器内科選びでは、以下のポイントを確認するとよいでしょう。
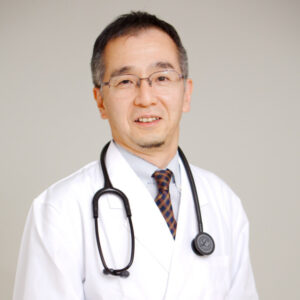
荒井駅前のぐち内科クリニック野口 哲也 先生
宮城県仙台市の「荒井駅前のぐち内科クリニック」 院長の野口です。
私は岩手県盛岡市で大学生活を送り、東北労災病院内科、東北大学消化器内科での消化器病学の修練、対がん協会での胃・大腸がん検診活動、そして、宮城県立がんセンターでの消化器癌に対するがん治療に従事してまいりました。消化器内科の専門家として診断から治療、特に内視鏡治療を行ってきました。最新の治療や全国的な治験や研究にも参加してきました。
これまで地域医療にも携わり、高血圧や糖尿病、肺炎や感冒、インフルエンザなど、様々な病で通院してくる患者さんの診療にも従事してまいりました。震災復興が進む、ここ荒井地区において、これまでの28年間の勤務医としての経験を活かし、地域の皆様の健康を支える医療、身近なかかりつけ医を目指し、少しでも貢献させて頂ければ思っております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
© ヨクミテ|医師監修の医療メディア, Inc. All Rights Reserved.